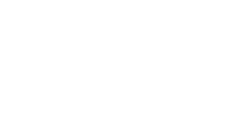多彩な受け付けチャネル
インターネットが受注チャネルとして存在感を増す中、電話というチャネルも引き続き重要性を保ったままです。一時は電話不要論まで飛び出ましたが、テレビなどの媒体との親和性や、年代を問わず使われる柔軟性が人気の秘訣でしょうか。携帯電話・スマートフォンの普及により、その場ですぐに電話をかけられる環境が整備されたことも追い風になっていると思われます。
その一方で、電話業務のアウトソースの流れは止まりません。社内には必要最低限な代表電話だけおいて、後は全て外注先に転送しているところも多いのではないでしょうか。大規模な通販会社であれば、コールセンター業務を丸ごとアウトソースしているところも多いでしょう。そのロケーションも様々です。都市部に展開しているところもあれば地方や海外を拠点に展開しているところもあったりと、コールセンターによって個性があります。
今回は、こうした電話業務のアウトソース先である、電話代行やコールセンター、受話業務会社の運営管理システムについて考えてみたいと思います。どういったポイントに気をつけて構築すべきか、いくつかのポイントで整理してみましょう。
Point.1 ICT、FAXとの高度な連携
ある程度の規模以上の電話関連の業務を行っていれば、既に何かしらのICTツールを使っていると思います。管理システムをそのICTツール上で拡張するのも一つですが、他のサービスや他のシステムとの統合を考えるのであれば、ICTツールと共存するかたちでシステムを構築し、高度な連携を行えるようにしましょう。
データの不整合や、二度手間の入力作業がないようにカスタマイズを施し、FAXなどの発信もシステムで行えるようにすると、さらに業務効率が加速的に上昇します。請求業務も統合管理するとなおのこと便利でしょう。請求書をWEBで確認できるようにすれば、請求書を発送するための一連の作業を省力化することができますし、顧客にとってもすぐに請求書が手に入るメリットがあります。システムの応答速度にもこだわってください。電話越しに相手を待たせるわけにはいかないため、秒単位で素早く対応する必要があります。システムの画面遷移のたびにロードの待ち時間が長く発生するのであればテコ入れが必要でしょう。
Point.2 冗長化で業務停止を回避
外部からの悪意ある攻撃や、一時的な高負荷、システムの不具合やネットワークの断絶など、システムが突然停止するリスクは避けることはできません。それが自社のコントロール不能な要因であれば、その事態が解消するまでの間は業務が完全に停止してしまうことになります。
そこでシステムを冗長化し、すぐに切り替えられるホットスタンバイの状態のシステムをもう一つ用意しましょう。データベースのデータやプログラム内容は常に最新に更新されるようにしておき、物理的なシステム設置環境も別にしておきます。自然災害含む意図しないシステムダウンが発生した際にはすぐに切り替えられるようにしておき、業務停止時間を最小化できるようにしましょう。
クラウドサービス上にシステムを展開することでこうした冗長化を実現するのも一つでしょう。災害対策がしっかりと施されたプランやサービス会社を選定することで、こうした業務停止リスクをおさえることにつながります。1日業務が停止してしまうと、その日の損害も大きくなるだけでなく、つながらない会社としての評判が、ずっと続いてしまいます。こういった損害のリスクは徹底的に回避すべきでしょう。
Point.3 IVR機能の顧客への解放
コールセンター業務を筆頭に、自動応答(IVR)サービスを顧客が利用していることも多いでしょう。こうしたIVRを手動で設定するのも柔軟で良いのですが、ある程度の設定であれば顧客自らができるように機能を解放するのも一つです。スタッフの手間が減りますし、結果的に費用を抑えることができ、顧客側のメリットもあります。
あまり複雑なことはできなかったとしても、基本的な番号選択や応答内容をカスタマイズだけで大半の自動応答のニーズは満たすことができるのではないでしょうか。自分の声を吹き込むことができるようにすることも良いでしょうし、その部分だけスタッフが代行するのも良いでしょう。また、昨今は人工音声も自然になってきているので、そうした人工音声で読み上げるようにするのも良いかもしれません。工数がかかるものについては、有償のオプションとしてサービスメニューに加えるのも良いでしょう。便利な機能だけに、自社のサービスの付加価値を高めるためにも、こうした高度な機能を安く簡単に利用できるようにしてみてください。
作業代行からビジネスパートナーへ
電話業務のアウトソースは、ただの作業代行のように捉えられがちですが、他にはない質やスピードを提供することで、かけがえのないビジネスパートナーのポジションを獲得することは不可能ではありません。
とはいえ、これ以上労働集約的な付加価値のあげ方ではすぐに限界がきてしまいます。システムの力を最大限活用し、人とシステムの高度なコラボレーションによる価値提供を目指してみてください。
開発スタッフのコメント